送料減額改定、ケミカル価格改定について
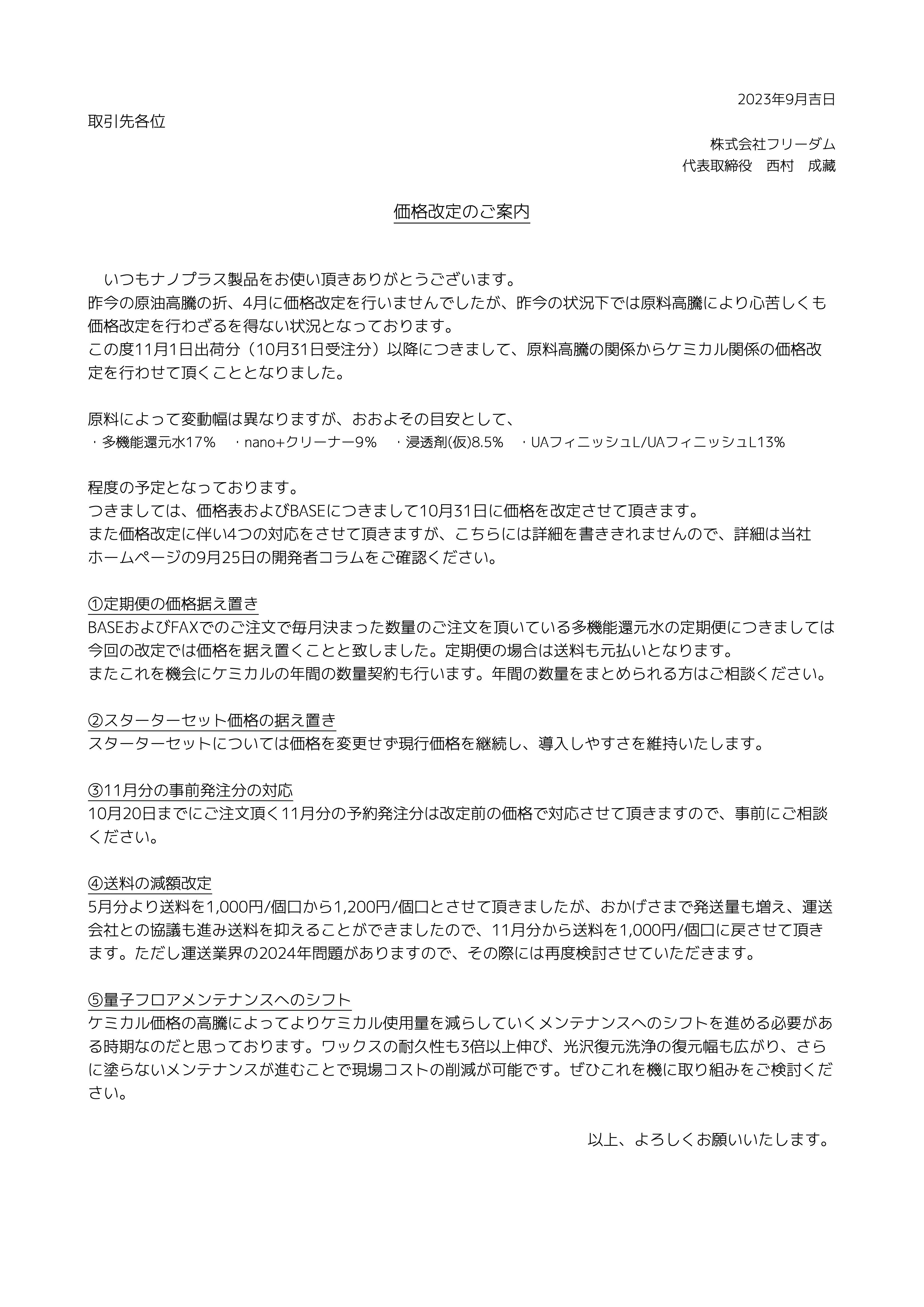
この度11月1日出荷分(10月31日受注分)以降につきまして、原料高騰の関係からケミカル関係の価格改定を行わせて頂くこととなりました。
原料によって変動幅は異なりますが、おおよその目安として、
・多機能還元水17%
・UAフィニッシュL/UAフィニッシュL13%
・nano+クリーナー9%
・浸透剤(仮)8.5%
程度となります
つきましては、価格表およびBASEにつきまして10月31日に価格を改定させて頂きます。
尚、新しい価格表はこちらになる予定です。
価格改定に伴い4つの対応をさせて頂きます。
①定期便の価格据え置き
BASEおよびFAXでのご注文で毎月決まった数量のご注文を頂いている多機能還元水の定期便につきましては今回の改定では価格を据え置くことと致しました。
定期便では最低1年間継続が条件となっていますが、現行価格でさらに送料分が安くなっています。
(途中で停止はできませんが、停止になった場合は通常の価格との差額が請求されます。)
こちらに合わせてUAフィニッシュLも定期便も設定いたしました。
極端な物価変動がない限りは1年間定期便の価格を据え置きで対応させて頂きます。
またこれを機会に年間の数量契約も行います。
具体的に数量をまとめられる方はご相談ください。
②スターターセット価格の据え置き
スターターセットについては価格を変更せず現行価格を継続し、導入しやすさを維持することといたしました。
浸透剤(仮)スターターセットについても同様です。
③11月分の事前発注分の対応
10月20日までにご注文頂く11月分の予約発注分は改定前の価格で対応させて頂きます。
・会 社 名:
・住 所:
・電 話 番 号:
・発注予定日:
・発 注 内 容:
をFAXください。
BASEでのご注文の方はHPのお問い合わせフォームかメール、インスタDMで事前にお知らせください。
④送料の減額改定
5月分より送料を1,000円/個口から1,200円/個口とさせて頂きましたが、おかげさまで発送量も増え、運送会社との協議も進み送料を抑えることができましたので、11月分から送料を1,000円/個口に戻させて頂きます。
ただし皆様ご存知の通り、運送業界には2024年問題があり、その時に運賃はあらためて変動があるものと思われますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また日付・時間指定も可能となっておりますので備考欄に記載ください。(※北海道を除く)
⑤量子フロアメンテナンスへのシフト
ケミカル価格の高騰によってよりケミカル使用量を減らしていくメンテナンスへのシフトを進める必要がある時期なのだと思っております。
量子フロアメンテナンスは量子技術によって、界面活性剤ゼロのメンテナンスは洗浄液のコストは結果的に変わらないとはいえ、ワックスの耐久性が3倍以上伸びることでワックスコストと作業時間の大幅な削減が可能になります。
ひと昔前のUAコーティングの耐久性は剥離が簡単なUAフィニッシュLで出せてしまうということで、光沢復元洗浄もより簡単になっていきます。
ぜひこれを機に取り組みをご検討ください。
量子フロアメンテナンスのセミナーの詳細はこちらをクリック
よろしくお願いいたします。
2023年09月25日 05:55










