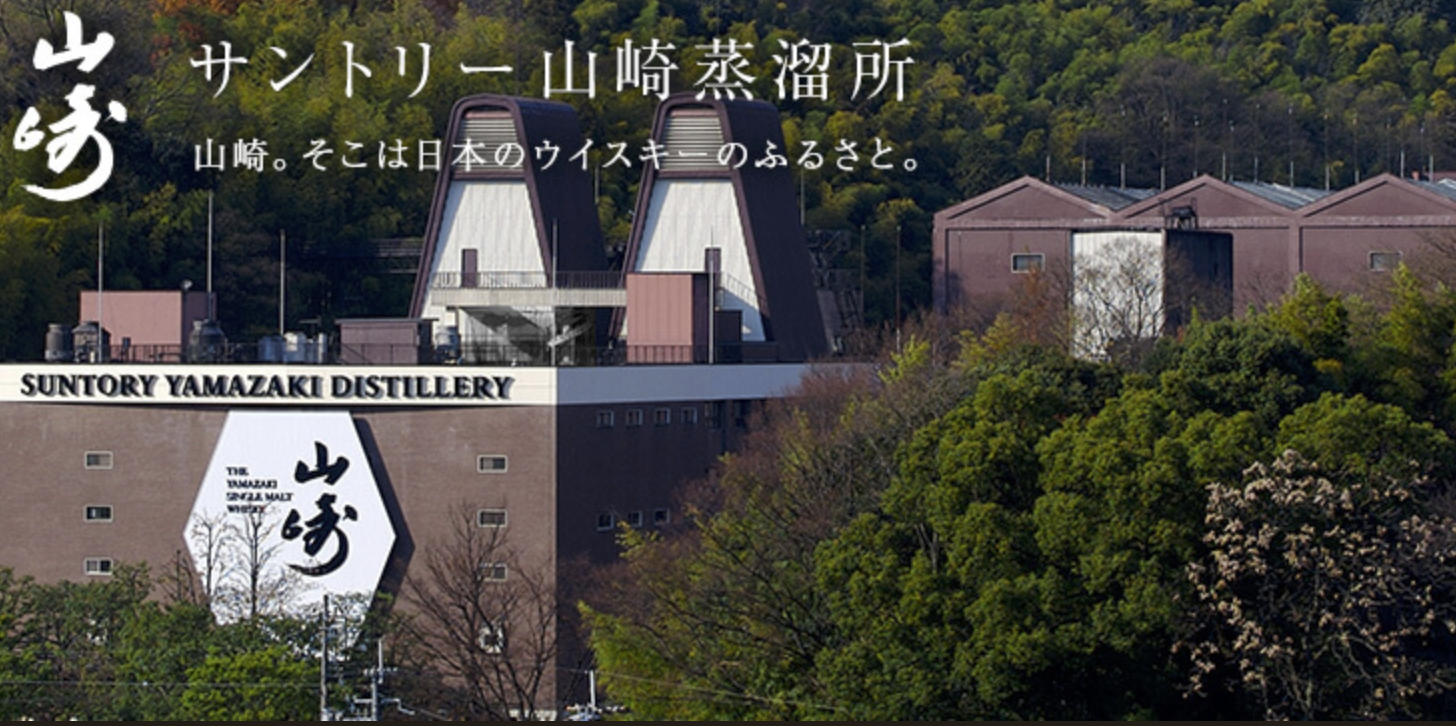11月ナノプラスセミナーのお知らせ
11月のセミナー日程のご案内です。大人数のセミナーではなく、1社のみ(4名様まで)のセミナーになり、参加される方の課題に合わせたオーダーメイドのセミナーとさせて頂きます。
導入前の方も申し込み頂けます。
尚、ナノプラス導入後3ヶ月以上経過されている方につきましては、実務的な経営の効率化などのご相談もセミナーで対応させて頂きます。
セミナー費用は無料です。
○11月16日(木)
1000〜1300 東京(日本橋事務所)
1530〜 東京ビックサイト(セミナーは行いませんが相談のある方は受け付けます)
(1420〜1520 講演会場B ワイズ・クルーさんのタイルカーペットの洗浄システムの講演に参加申し込みしました)
以降の予定は入れていませんので、何かあるようでしたらご連絡ください。
○11月17日(金)
1200〜1500 東京(日本橋事務所)
1500〜1800 東京(日本橋事務所)
○11月18日(土)
1200〜1500 名古屋
1300〜1600 京都
1400〜1700 梅田
※いずれか1枠先着順
訪問しての開催も可能です。
他日程につきましては現在調整中です。
他日程、他エリア、オンラインでのセミナーもご相談に応じておりますので、こちらよりご連絡ください。
・先着順とさせて頂きます。
・ご参加の方は必ずHPを一読の上、お申し込みください。
・セミナー内容は参加される方の課題により決定しますので、セミナー参加への目的を明確にお願いいたします。
上記以外のエリアにつきましては、ご依頼を頂いてから別途日程を調整させて頂きます。
いずれもご希望の方はこちらから申し込みください。
皆様のご参加をお待ちしております。
2023年10月20日 15:33