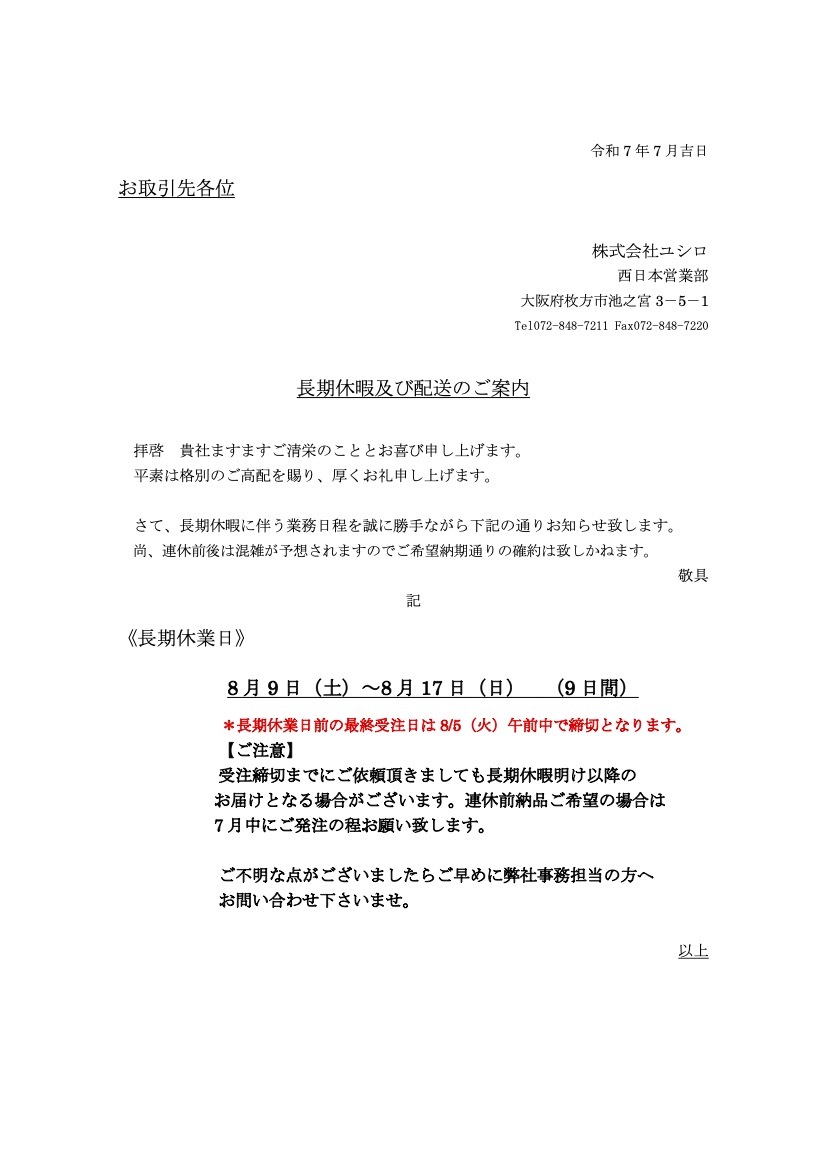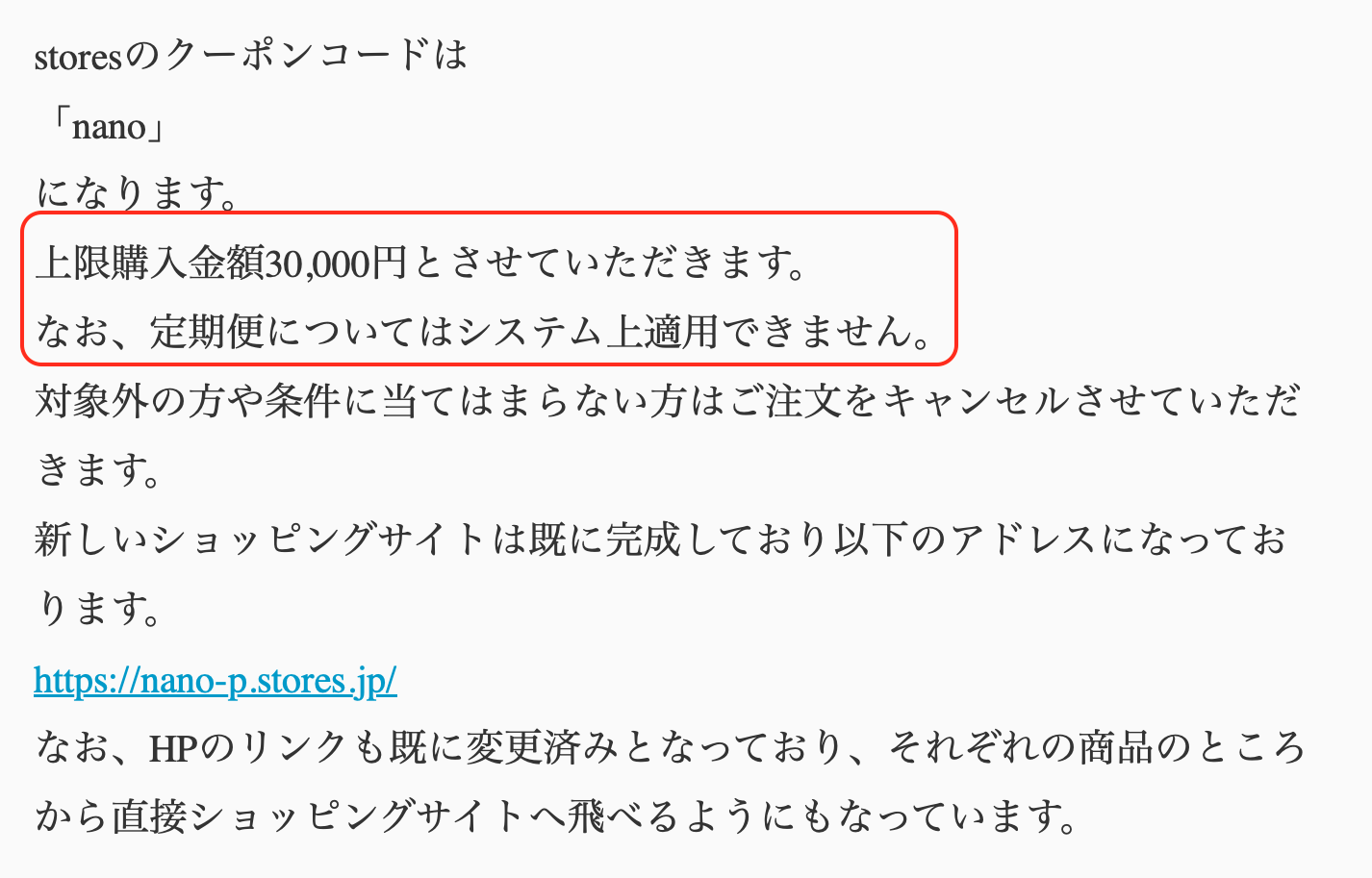日常の洗浄液によるワックスのゆるみ 2
前回からの続きです。うちの事務所では毎日床に水を撒いて回収して床を洗っていますが、
・UAコーティング
・UAフィニッシュL
・finish+
で実験したところ、アルカリ電解水での緩みやすさは
1 UAフィニッシュL
2 UAコーティング
3 finish+
の順番になりました。
finish+はアルカリに強いですから、洗浄で油汚れが多い場合にアルカリ電解水を併用しても艶ボケしにくいと言えます。
日常清掃においてはナノバブル2やまないのきよみずを併用することにより水だけで汚れを落とします。
さらに洗浄力を補うためにマイクロファイバーパッドのトレールパッドを併用することで油汚れに対しても洗浄力を担保します。
ナノバブル2やまないのきよみずは界面活性剤を含まないどころか化学式ではH2Oですから洗剤のようにあとで汚れが付きやすくはなりません。
洗剤ほど洗浄力がなくても汚れず汚れの量が少ないからそれで十分なのです。
またH2Oですから汚れは別としても洗浄液としての環境負荷はなく、ナノバブル水もまないのきよみずも水道水よりも良い水になっているので水道水より環境に良いもので洗っていると言えます。
ワックスにも環境にも良いもので現場を管理できればこれほど良いことはありません。
2025年07月31日 00:00