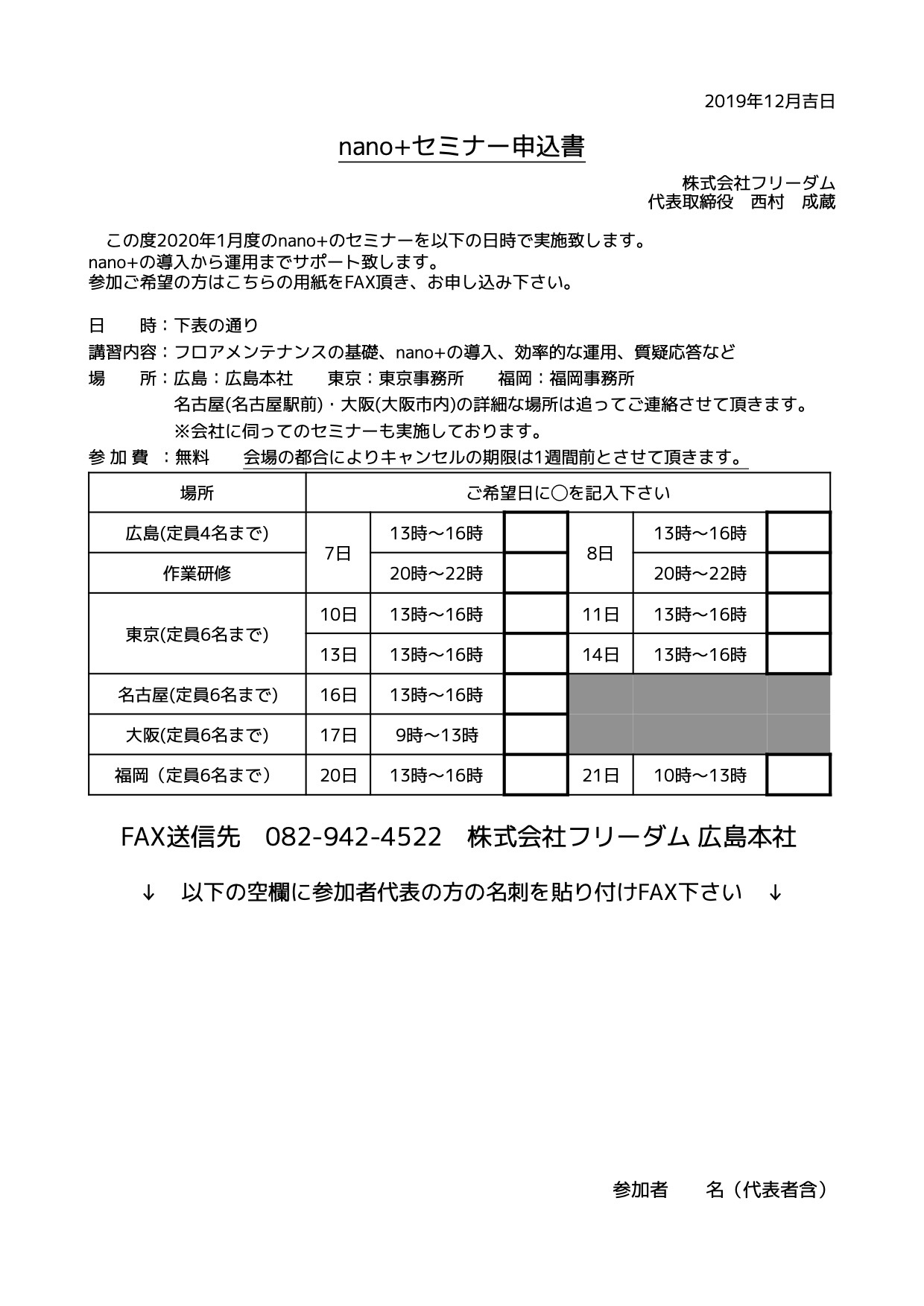正しい比較
安全で環境に優しい洗剤とか、アルコールに強いワックスとか、いう表現ほど抽象的なものはありません。例えば亜鉛フリーワックス
剥離が簡単と書いてありますが、亜鉛フリーになると逆に剥離性は悪くなることは設計している人間はわかっているので、それでも大丈夫ですよという意味で書いています。亜鉛フリーのワックスにしては剥離しやすいという意味であって、これは普通の樹脂ワックスに比べて剥離が簡単という意味ではありません。
実際に剥離性は悪いのです。
アルコールに強いワックス
以前実験したことがありますが、R社の耐アルコール病院用ワックスとY社の高濃度樹脂ワックスを比較しましたが、Y社の高濃度樹脂ワックスの方が良い結果が出ることも。当社の製品でもアルコールでよく比較されるのはUAコーティング。
そういった病院用のワックスと比較して別物の耐アルコール性を持っています(もちろん限界はありますが)
高耐久性ワックス!とか、環境に優しい!とか書いてありますが、何と比較してどうか?
その比較対象で比較が正しいのかということでその判断が合っているか間違えているかというのは変わるのです。
従来比何%!と書いてあってもその従来のものを使っていなければ分かりませんし、どういった状況下でそれをどのように検証したのかによっても変わってきます。
安全性であれば数値で示したり、nano+の場合は人間が素手で使っても手が綺麗になるレベルの安全性を一つの指標にしています。
人肌で問題なければ多くの建材で問題は起こる可能性は低いのです。
メーカーの言うことや書いてあることをそのまま受け止めず、なぜそうなのかというのを考えてみるとものも見え方が変わってきます。
2019年12月23日 13:05