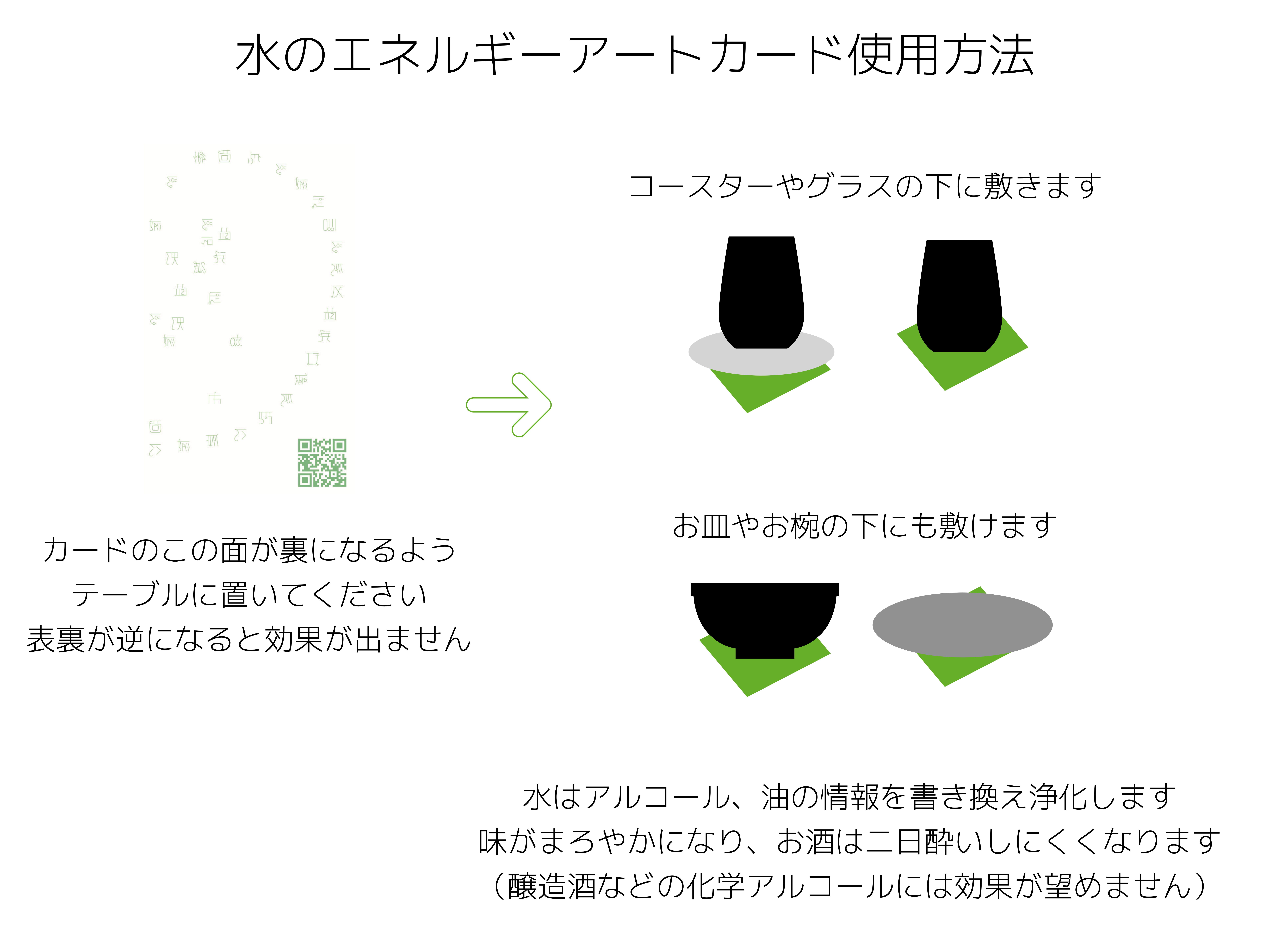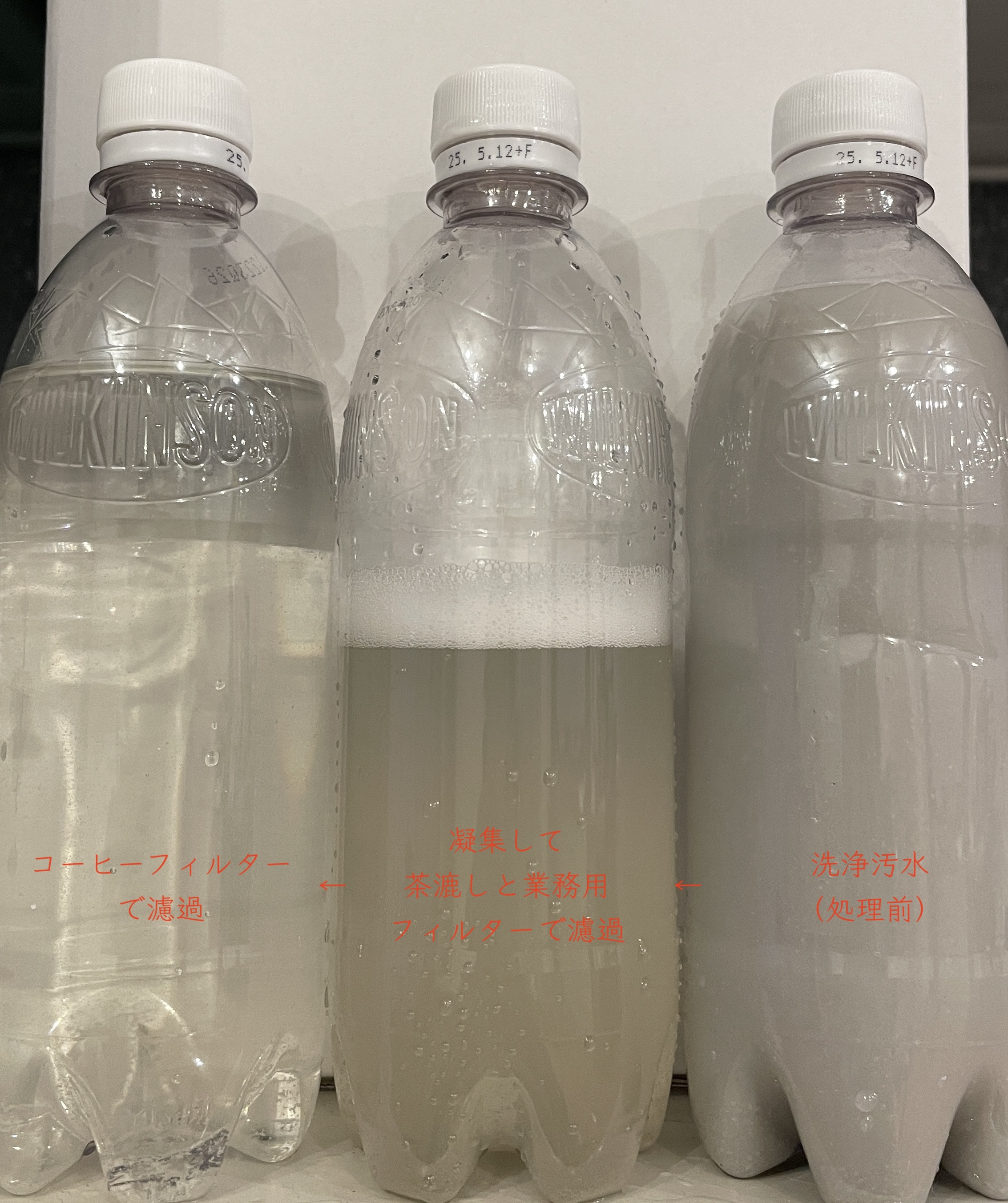ワックスのコスト計算 3
ワックスコストの話をしてきましたが、finish+が少し高いといっても実質的にはさほどでもないということがわかると思います。今回は実際のワックス消費量の実例です。
うちの現場用のものですが、UAフィニッシュLからfinish+にすべての現場を塗り替えました。
わたしが行く現場とそうでない現場があり、わたしが行く現場は一度塗るとほとんど塗らなくなってしまいます。
うちの車と資機材を持っていってもらって作業もお願いしているのですが、具体的なことは言わずに多機能還元水250倍で洗ってfinish+を1層塗布として指示を出していません。
これまでUAフィニッシュLの時は月間4Lボトルで8本くらい準備して実質消費しているのは6本くらいでした。
それが3本くらいに減りました。
意図的に塗らないことを選択させたりはしていませんが、同じように作業して同じように塗っているだけです。
その原因は光沢復元洗浄による平滑さの向上にあるといえます。
・nano+クリーナーを使わないから表面がわずかでも荒れない。
・界面活性剤がゼロになるから耐久性がアップ。
・より平滑に洗い上がる結果となり、より薄塗りに。
わたしが現場に行かないからこそ、塗らなくても良い場合でも塗るよう指示を出して品質を担保するという管理方法をとっています。
それでも消費量が半分になっているということはそれだけ薄塗りになっているということになります。
意図的な薄塗りではなく、伸びが良いので結果的に薄塗りということですね。
ただでさえ多機能還元水で減膜できるfinish+を薄塗り管理するとビルドアップして剥離なんてことには永久にならず、むしろもっと塗らないと追いつかないという状況で、先日は2層塗るということもありました。
次回へ続きます。
2025年03月20日 00:00