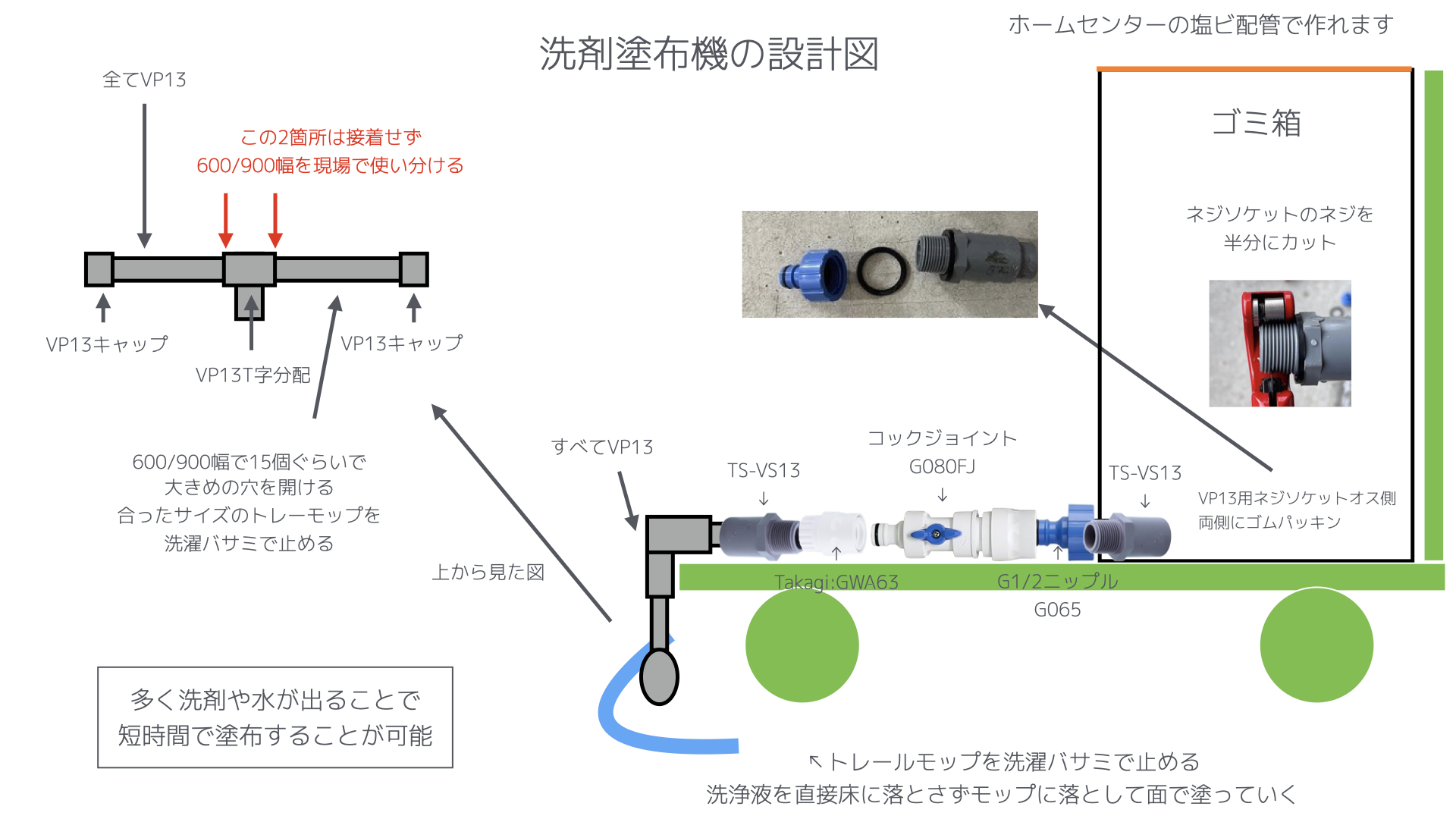何のために学ぶのか13
前回京都の老舗の話をしました。事業はそういった経営の部分から組み立てるのであって現場から組み立てるのではありません。
うちの会社の場合だと「単発の仕事はせず、定期の仕事しかしない」をいう原則があります。
それは経営の安定もありますが何より利益率です。
本来1回かがりの単発の仕事は単価が高くないといけませんが近年ではさほどそうでもありませんし、はじめてやる現場といつも定期でやっている現場では作業した際の作業時間は大きく変わり、それは利益率に反映されます。
そして定期の仕事だと、ちゃんと維持してしまえばやればやるほど利益率は上がっていきます。
これはワックス床やカーペット床は顕著にでますが、マンションの共用部のノンスリップシートの洗浄でさえもそうです。
年2回作業していますが、水で土砂などを流して部分的な汚れを擦れば終わるのでもはや水遊びレベルです。
そうなってくると営業ターゲットも変わってきますね。
現代人はあれもこれもやりたがります。
仕事でなくても現代人はあれやこれやいろんなことをしてまるで視線誘導されているように本来集中すべきことや見るべきものに集中できていません。
ジョブズは毎日着る服も同じものを数セットにして服を選ぶことをやめたのも有名な話です。
人生は決断の連続です。
何を食べるか、どの服を着るか、靴は右足から履くか左足から履くか、あまり知覚できていませんが決断するたびに精神はすり減っているとも言われます。
我々の現場のそれを落とし込んでしまえば、定期の床の現場を多機能還元水で洗ってワックスを塗った方が良い状態ならfinish+を塗るという選択肢のない現場管理へ行き着きます。
とてもシンプルでわかりやすく、誰がやってもさほど品質のブレは出ません。
経営も営業も現場も本来やるべきことにフォーカスし、それ以外の部分はやらないことがこれからの時代は重要です。
そもそも本質的には自分にしかできない仕事だけをやるのが仕事であって、誰でもできる仕事は他の人にやって貰えばよいのです。
他の人にやってもらうために誰にでもできるというのがポイントになってきます。
そして空いた時間で自分にしかできない、自分がやりたい仕事に注力すれば良いのです。
これからの時代は自分がやりたい仕事、自分にしかできない仕事が注目される時代になっていきます。
2024年09月12日 00:00