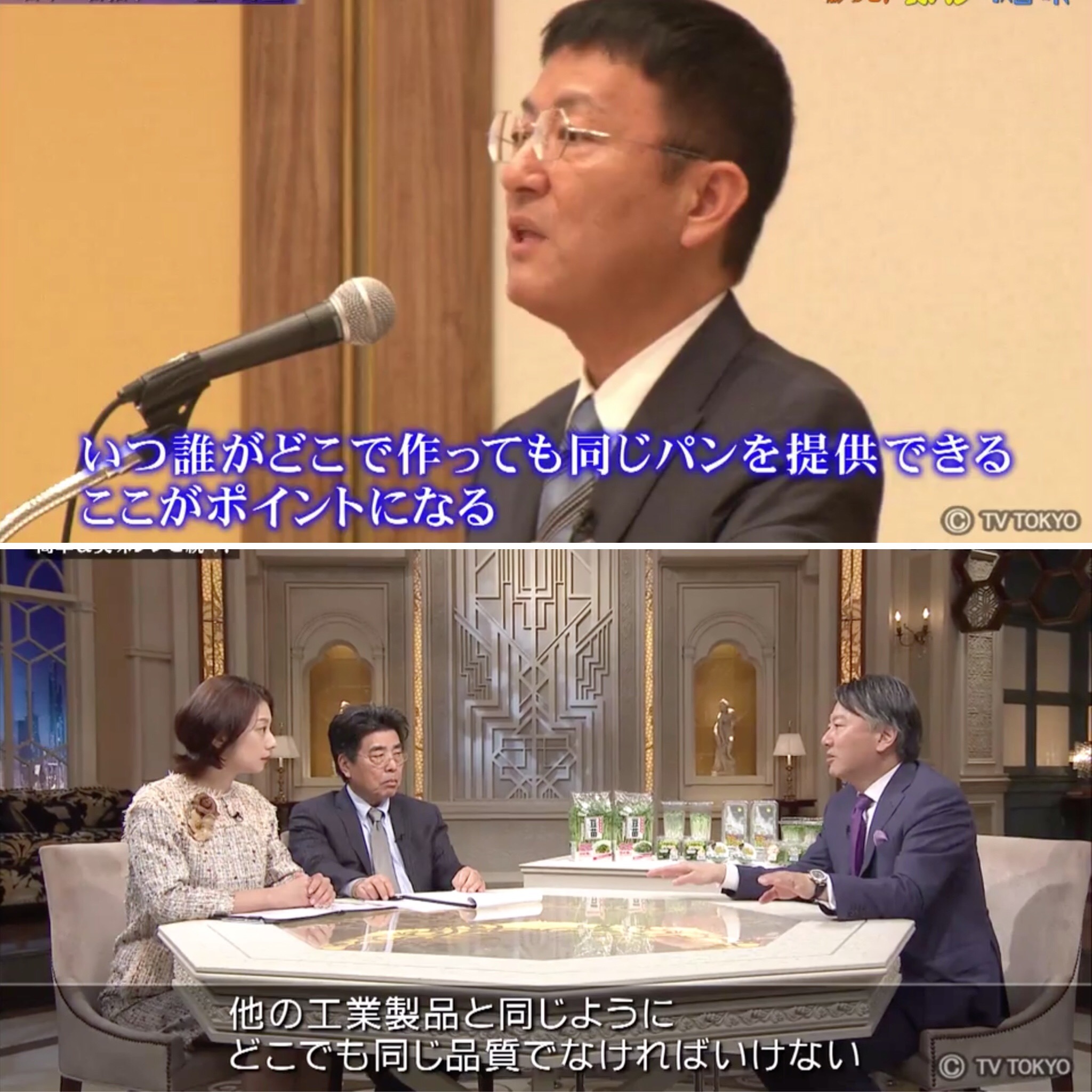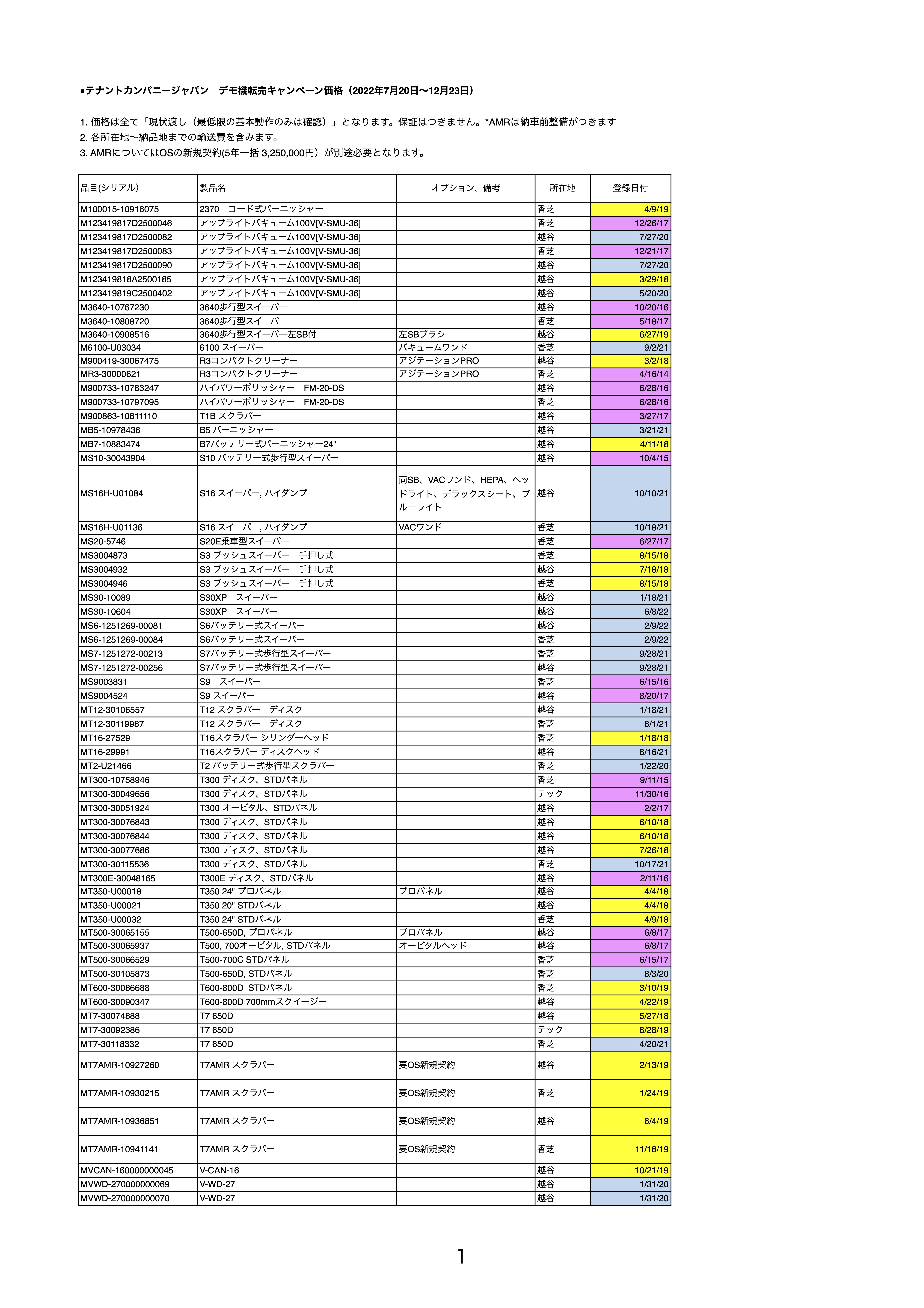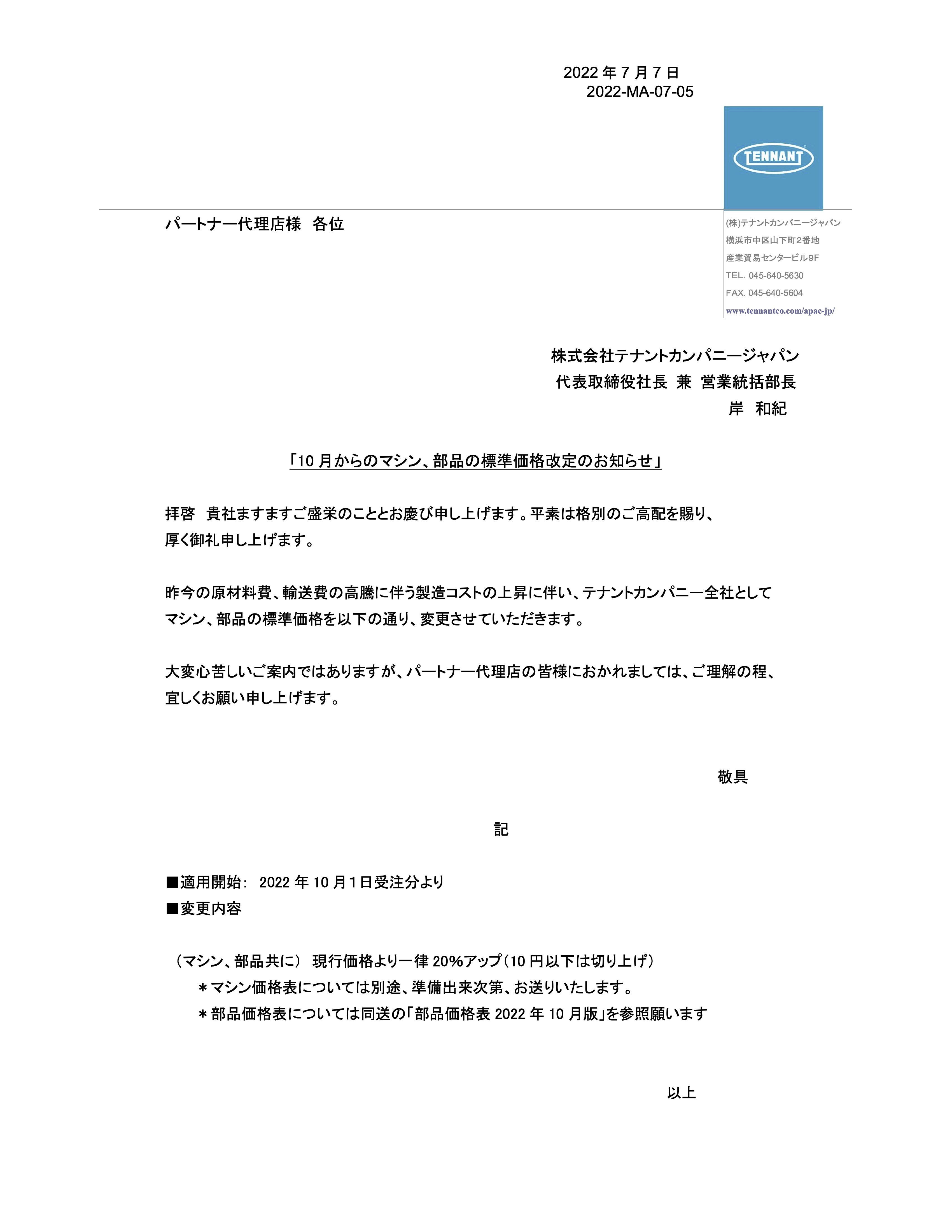2019年4月29日の記事のアーカイブです。
元記事は
こちら
先週の記事では、習慣化すること、選択肢を減らすことで品質のバラツキを減らすという話をしました。
今回はそれを使って現場に落とし込むかという話について書かれている記事です。
↓ここから過去記事
決断と習慣の話その1の続きです。
前回の話は、決断・我慢・無理をすると精神的に負荷がかかるので続かないということ。
また人は疲れると脳が省エネモードになるので、人間は「習慣」つまり慣れで動きます。
これは脳がそう動くので致し方ない部分もあるかもしれません。
清掃の現場で作業前はともかく、ずっと考えながら作業する人はまずいないでしょう。
作業中は基本的には無意識です。
病院清掃や24時間スーパーのように、常に人の往来がある現場で疲れやすいのは、無意識でなく周りを意識しながら作業しているからですね。
周りを意識すると作業に集中するのは本当に大変です。
なのでこれまでの経験で蓄積された間違えた作業方法(つまり癖)を正したり、新しいものを導入するには「習慣」を変えていく必要がある!
というのは毎月参加する勉強会で学んだ、某大学が「習慣」について研究している話。
実際にうちのスタッフも未経験者の方が「習慣」がないので育つのが早い傾向にあります。
また会社によっては、この現場はnano+だからこの作業方法、こっちの現場はこれまでの作業方法とやってしまうことがありますが、これはこの「習慣」の法則からいうと、身につかず習慣化されないことは明らか。
「習慣」により自動操縦
組織には人と一緒で、明文化されない「習慣」が存在し、「習慣」により自動操縦されています。
なので、「習慣」を変えなければ同じ結果が導き出されます。
よく「会社のトイレの清掃をすれば業績が上がる!」
なんて経営者のセミナーでやっていることがあります。
清掃会社はそれが仕事なので業績が上がらないとおかしいなと思ったことがあります。
しかしこれはそういう意味ではなく、「トイレ清掃を毎日行う=決めたことを決めた通りにやる」
ことが「習慣」を守る意志力が高くなるので、会社の決めた「習慣」を決めた通りにやることで組織が機能し、業績が上がりやすくなるということだと思います。
簡単な1つの「習慣」を守ることで「習慣」を守る意志力が高まると言われています。
仕事をする以上は良い「習慣」を身につけなければ良い結果は出ません。
簡単なこと1つ守れない組織が、大きなたくさんのことを守って実行できる訳がありません。
良いルーティンも必要
プロゴルファーや野球選手にはルーティーンが人が多いですね。
イチローが試合の朝カレーを食べるということだったり、バッターボックスに入る時にやるあれです。
現場をやる上でのルーティーンとは?
学生の頃大工さんのバイトをしていましたが、大工の世界は8時、10時、12時、15時に休憩をしてミーティングです。
進捗の確認などを行っていますが、必ず毎日これを守ります。
これもルーティーンなんですね。
ルーティンも「習慣」ですね。
この「習慣」を守っているから現場のルールもきちんと守られています。
習慣は消すことができない!
ので、はいリセット!とはいかないのです。
これまで生きてきた長い経験でできているものですから。
しかし、良習慣を上書きすることができます。
その際には必ず具体的なメリットが必要になります。
作業が楽になる、早く終わる、剥離がなくなる、給与が上がるなど。
心理学では、人は快楽より苦痛からの解放を選択すると言われています。
快楽(給与が上がる)、苦痛(作業が楽になる、休みが増える、早く終わる、剥離がなくなる、手が荒れないなど)ですので、それを気づかせてあげる必要があるんですね。
平均66日で習慣化
人により異なり、30日〜180日程度と言われていますが、平均をとるとおよそ66日で習慣化されると言われています。
昔の人は上手いこと言うなと思うのは、いわゆる体が覚えるというやつです。
最初から全てを完璧にできてしまえばすぐに結果は出ます。
2,3人の組織なら社長が先頭を切って作業してできるでしょう。
しかし組織が大きくなるとそうは行きません。
なのでnano+は3ステップでの導入をオススメすることとしました。
ここではワックス床の定期清掃で説明します。
①の部分
まずは↑の資料にある①の部分。
使うものに慣れること。
作業されるスタッフさんに結果を求めないで下さい。
得てして経営者側が現場に求める結果は高くなりがちです。
洗剤やワックス、パッドはこれまでも変えられて試行錯誤はされていると思います。
まずは作業が楽になるからということで、これまでの作業方法は変えずに資材(洗浄液・パッド・ワックス)だけを変えて下さい。
それでもある程度黒ずみも取れますし、ワックスの密着率も上がるので、これまでよりは少し良くなりますからその部分だけを見てみて下さい。(ちなみに最初からできる会社は最初から全て①〜③までやって頂いて大丈夫です。)
1,2ヶ月程度してから作業はどう?と聞いてみて、楽になった!という回答が出たら②へ。
この楽になった!が重要で、これが使うことによるメリットです。
これをやれば楽になる→次のことをやればもっと楽になるのだろうか、と思ってもらわないと次に行けません。
②の部分
①が確実できるようになると、ポリッシャーの使い方を変えてみると作業が早く終われるよ、と教えてあげます。
まずは
この資料を見せてあげて
こちらの動画を見せてあげるといいでしょう。
資料の意味はわからなくてもいいので、ポリッシャーのパッドの回転方向に縦に洗浄しましょう。
縦横を変えるだけでポリッシャーが止まって向きを変える回数が減るので、洗浄時間は短縮されます。
これに味をしめたら③へ。
③の部分
洗浄液の先塗りはポリッシャータンク出しに慣れている人には相当に抵抗があるようです。
しかし本来は必ず先塗りしなければ剥離清掃を永久になしにはできません。
これは
洗浄の方程式を見れば一目瞭然。
ただ洗浄液の先塗りによってポリッシャースピードを上げることができるので、作業を早く終われるようになります。
先塗りは手間と思われがちですが、ポリッシャータンク出しで同様の品質を出そうとするとポリッシャースピードはかなり落ち現実的ではありません。
つまりは品質がイコールではないのです。
ポリッシャーを回すこと、ワックスを塗ることは仕事ではありません。
極論を言えば作業をすることが仕事だとも限りません。
良い被膜を作りそれを維持すればお客様から管理費を頂くことは可能です。
むしろ単価が上っても作業回数が少ない方がいいと言われるお客様もいらっしゃいます。
つまり綺麗であればなんでも良いが、汚いとなんでもダメ!
やって汚いならやらない方がいいということなんですね。
①②が習慣化されたことで、決まりは守るという意志力は上がっていますので、ここまでくれば素直にいうことを聞いてくれると思います。
この3ステップは他の業務にも応用できます。
毎日小さなことからでもいいので習慣化していきましょう。
良い組織の「習慣」は良い循環を生んでくれます。
決めた「習慣」は100%実行!
ただし、「習慣」づけることが目的ですので、必ず100%行うことが絶対条件です。
もし①の導入が難しければ、どれか1アイテムからでも始めていきます。
100%できそうだったら先に進めるようにして下さい。
99%では守っていないので、0%と同じなのです。
そして現場ですべきことは、管理者が決めた通りの作業を確実に時間内にこなすこと。
これも守れるようになりますので、品質と収益性の高さが両立でき、クレーム発生率が下がるので管理も楽になり、管理者は担当物件を増やすことも可能になり、管理者の生産性も高くなります。
↑過去記事ここまで
習慣化でもっとも大切なことは、簡単で良いので決めたことを必ず守ること。
簡単のレベルで言えば、マラソンを始めるのならまずは毎日マラソンシューズを履くことです。
そんなところからと思うことかもしれませんが、そこからでも必ず決まったことをやってという事実が大切なのです。
そしてそれを広げようとした場合に、これに決めたからこれを使えと言うのではなく、こっちを使った方がしんどいのから解放されて楽になるよという進め方です。
人は快楽と苦痛の解放の二択になった場合、苦痛からの解放を選ぶことが多いようです。
「あのしんどい剥離作業から解放されるよ」というのは実際に作業する人には刺さるのです。
これは既にナノプラスを使われている方には当てはまる話ですが、現場に行って今日はどうやって作業しようかと考えるのはそこで選択肢を生みます。
規模が大きくなればなるほど、洗ってUAフィニッシュLという分かりやすい使用の方が色々面倒がないのです。
2022年07月14日 05:55